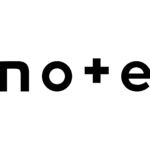#00001 私は私と私の環境である
私は私と私の環境である
――私は私と私の環境である。もし私の環境を救わなければ、私自身も救えない。――
原文はスペイン語で
«Yo soy yo y mi circunstancia; y si no la salvo a ella no me salvo yo.»
であり、冒頭で紹介したのはその日本語訳である。
この言葉は、いわゆる「名言」として、哲学書や思想本を好んで読む人たちの界隈では割と知られており、“とある人物”が“その著書”の中で繰り返し述べているものだ。しかし僕が高校生までに読んだ教科書の中では見たことがないし、たぶん今でも載っていないだろうと思う。つまり、誰もが知っている人物ではない。
名言について調べる前にしてほしいこと
その名言の主が誰であるかを知りたくなってうずうずしてきた人はこの言葉をそのままコピーしてGoogleで検索すればいい。著書名もすぐわかるはずだ。この言葉について述べた解説の類もたくさん見つかるだろう。
しかし、検索すればすぐ獲得できるそういう知識を求める前に、「うずうず」する気持ちを我慢してこの“言葉そのもの”を時間をかけてじっくり味わってほしいのだ。
名言についての”知識“がなくとも、解説を読まなくても、背景を知らなくても、”名言それ自体“をじっくり味わうことによって頭の中に湧き起こってくるイメージがあるはずだ。
そのイメージを膨らませることこそが大切だと僕は思う。
はっきりとイメージを頭の中に描けるようになってから、「名言」の出所である著作に触れる方が深くて能動的な読書ができるだろう。たとえ、著作に書かれている実際の内容が予想した内容と同じであっても、違っていてもだ。
僕はそう考えているので、ここではその「名言」についての解説は行わない。名言の主の名前すらここに書くのは嫌だ。
僕は知識欲が欠落した、思考欲だけの人間
どうしても検索したいという思いを我慢できない人は、以後、僕の書く文章を読まない方がいいと思う。僕は読者の知識欲を満足させるような文章は書けないのだ。
僕は思考の道筋を丁寧に記述することを心がけている、言うなれば「思考欲」だけの人間に過ぎず、知識欲が欠落した人間なので、知識を求めている人を満足させることはどだい無理である。
そういう人間が僕なのだ。
ここまでは僕がどんな人間であるかについての自己紹介のほんの“さわり”として書いた。確実に失望するだろう読者に対しては、最初の時点で僕がどのような書き手であるかについて前もってちゃんと知らせておくべきと考えたのだ。
これから僕はnote.comと自身のブログサイト(https://walkingplanner.com)にて同じ文章を公開し続けるが、この後も読みたいと思う人はだいぶ減ったことだろう。
「名言」との出会い。思考の始まり。
さて、僕は、今から40年ほど前、つまり二十歳頃にこの「名言」と出会ったが、この言葉にたちまちのうちに強く惹きつけられた。それまでに、僕は明確な表現を獲得できないながらも既に頭の中で朧げながらもかなり近いイメージを掴みかけていたので、「これだ!」と思ったのだ。実に見事な表現だと思った。「私と私の環境」なんて表現はとうてい僕の中からは出て来ず、そのために随分長い間もやもやとした思いを抱えながら生きていたが、この表現に出会って、頭の中の霧が晴れるような思いがした。
この表現との出会いは僕の人生の中で特に感動的なものだったが、この言葉は意識の中核部分に根を張るようになり、それ以後、僕の自己と世界についての認識は、時間の経過とともにその後大きく変わり、物事を見たり判断したりする時の「視座」も変わり、当然言動のすべてが変わった。
思えば、この時から僕は意識的に思考するようになった。「思考することを思考しながら思考する」ようになったのもこの頃である。
『葛藤するインターネット』の出版。思考の土台の確立
この名言との出会いから約12年後の1997年に僕は『葛藤するインターネット』という本を世に送り出した。この本を執筆する上での視座は「名言」に出会ってから12年の間により納得できるものへと練り上げられ、さらに執筆の過程で仕上げられたものである。
この本を脱稿した時に視座は完成したが、この時に僕は子どもの頃からずっと感じていた疎外感から完全に脱することができたように思い、救われたような気がした。これは32歳の時のことである。
それから現在までに、僕は28年ほど生きているのであるが、この間、いろんなことがあったけど、精神的に迷うことはなかった。思考の土台を築いていたからだと考えている。
「思考することを思考しながら思考する」ことを意識して到達した思考の土台は揺らぎにくく長持ちするようだ。借り物でない自分独自の思考と認識の土台を30歳頃という若いうちに築けたことは幸運であったと思う。
自分の思考の道筋を記述するだけという思想スタイルの確立
『葛藤するインターネット』は、書店では「現代思想」と「パソコン」の本として分類されていたが、この中には丸山眞男氏の名前はどうしても出す必要があったので出したけど、しかし丸山眞男氏の思想には一切触れず、それ以外の思想家や哲学者は名前すら登場しない本であった。
高名な思想家や哲学者、知識人の名を登場させて、彼らの論を批判したり、彼らの言説に仮託して自論を展開したら、思想本・哲学書の類を愛読する界隈の読者たちは「反応」し、本はもう少しは話題になってもっと売れたのかもしれないが、僕はそのようなことは一切しなかった。それが思想を語る時の僕のスタイルなのである。
要するに、考え抜いて自分の血肉になった考えを、しっくりくる言葉を使って表現しさえすればよいのであって、ビッグネームたちの名前を出したり、彼らの言説を引用したりする必要があるとは僕は考えないのだ。
それに、ビッグネームたちの名前を出せば、その名前に反応して寄ってくる人たちがいるだろう。例えば、「アホンダラー」という有名な思想家がいるとして、僕が「アホンダラーも述べているように、・・・・・である」などと書きでもすれば、僕は「アホンダラー」について論じたい人々に囲まれてしまい、「僕の環境」はたちまちのうちに救い難い状況になり、そして僕自身が精神的に救われなくなるだろうことはわかりきっている。
あるいは、こちらがビッグネームの名前を出さなくても、「あなたの考えはアホンダラー的ですね」などと言って、アホンダラー論を語りたがる人がまとわりついてくるので、アホンダラーを思い出させるような言葉は極力避けて自分の考えを記すことにしてきた。
アホンダラーはひたすら思考に没頭し続けた人物で、その結果、思考の軌跡たる著作を多く残してしまうとその名が多くの人々に知られるようになり、つまりビッグネームになってしまうと、アホンダラー本の愛読者がこの世に登場するようになる。彼らはアホンダラーを消費することはあってもアホンダラーのように思考に没頭することはない。
思想本を消費する人たち
思想本を消費することと、思考に没頭することの間には雲泥の差がある。思想本を消費する人は思考に没頭できない。
思想本を愛読する読書人で、たくましく思考している人を僕は一度も見たことがない。膨大な本を読んできた人を今まで何人か知っているが、自ら思考しようとしない単なる「物知り」でしかなかった。
「あなた自身の考えは?」と質問すると彼らは例外なく絶句する。
知識に汚染された「汚染民」から影響を受けない「私の環境」を構築すること決意。
僕の知り合いの中には、いわゆる「高学歴者」とか「インテリ」と見なされている人も少なくないのだが、そのほとんどがこの手の単なる「物知り」である。頭の中が知識に汚染されていて、思考する力のみならず思考する意志も失っている状態。
彼らのことを以下で「汚染民」と呼ばせてもらう。少々きつい呼び方かもしれないが、他の呼称を思いつかない。じっさい、知識に汚染されているとしか僕には考えられないのだ。「汚染民」の生態については、次の稿でじっくりと述べる。
たぶん、「思考できない人間を『汚染民』と呼ぶとは何事だぁー」など言って糾弾されることはないだろう。特定の人物に対して「あなたは『汚染民』だ」などと僕が言わない限り反発はないはずだ。もし、糾弾してくる人が現れたら「あなたの頭は知識で汚染されているんですか?」と聴いてみるつもりだが、「そうです。私の頭の中は知識で汚染されているんです。」と返してくる人がいるだろうか。
僕の経験では、「汚染民」のような、強めの用語を使い続けると、思考している実感を持てていない人たちは離れていき、彼らを相手にする必要がなくなる。
『葛藤するインターネット』を執筆しながら、僕は知識に汚染された人々から影響を受けない「私の環境」を再構築することを決意し、出版後、人間関係を整理し、当時僕は大学院の最終学年に在籍していたが、汚染民の巣窟である大学から抜け出した。
以後、僕は汚染民たちにまとわりつかれることなく、思考に没頭できるようになった。
「第1環境」
ちなみに、「私の環境」の中で、思考に没頭するための環境が僕にとって最も大切なもので、これを僕は「第1環境」あるいは「私の第1環境」と呼んでいる。
「私の環境」は解決するのが難しい問題で満ち溢れているが、これを救うためには問題解決について思考に没入する第1環境が不可欠だ。しかし、第1環境は「汚染民」たちによって容易に占拠されがちだ。
これがあらゆる問題の中で最も厄介な問題であろう。問題の解決を困難にさせる問題だからである。
しかし、僕は、僕自身にとっての「私の第1環境」を変えることは、発想を変えれば意外と簡単であることに気がついた。特に、インターネットが普及した環境においては、である。
実際、僕は第1環境を再構築するための方策を実践し、思った通りの結果を得ている。僕がやったことは次の稿で述べるが、同じようなことを実践できる人はかなり限られるはずである。そもそも実践しようと思う人はほとんどいないはずだ。しかし、「そんなことはできるはずがない」と思う人は星の数ほどいるだろう。彼らの正体は実は「汚染民」そのものである。すなわち、思考する力のみならず思考する意志も失っている人々だ。思考する意志があればその可能性をはなから否定せずに、模索し始めるはずだからである。
「汚染民」を大量生産している学校という環境
次の稿では「汚染民」のことについてももっと詳しく述べるつもりだが、ここで少しだけ書くと、「汚染民」は「学校」で大量生産されている。
学校で生産された汚染民のうち、特に頭の硬い汚染民が教師になって、次の世代の汚染民を再生産するという再生産システムについても詳述するつもりだ。
「自己の領域」
次の稿では、「自己の領域」という概念についても述べる。これは僕独自の概念だが、僕は人が自分の問題として思える領域を「自己の領域」と呼んでいる。領域の広さは人それぞれ異なり、皮膚で囲まれた空間しか「自己の領域」だと思えない人もいれば、宇宙全体を「自己の領域」だと自覚している人もいる。
自己の領域が狭いか広いかによって、人の言動は大きく変わってくるが、「汚染民」の自己の領域は極端に狭い。
冒頭で示した
――私は私と私の環境である。もし私の環境を救わなければ、私自身も救えない。――
という「名言」は自己の領域が通常よりかなり広い人物が語った言葉である。
僕は、地球全体を自己の領域であると実感している人々に向けて、これからずっと文章を書いていくつもりである。